福井赤十字病院 第3回研修医症例検討会を開催しました。
初回は初期研修医1年目 持田京汰 先生が『研修医とともに学ぶ非専門医/医療スタッフのための虫垂炎診療』の演題で発表しました。
複数診療科の医師、当院へ実習中の福井大学医学生のほかコメディカル計30名が参加されました。テーマに関する専門医として、消化器外科 坂本裕生 先生、放射線診断科 都司和伸 先生に御指導頂きました。症例選定および全体の構成などについてはリウマチ・膠原病内科/腎臓内科 鈴木が継続して担当しております。
「非専門領域における達成目標は学生、研修医、指導医全て同じ」というコンセプトのもと、参加者全員が今回のテーマの専門医から学びました。
カンファレンスは3部構成で、1. 症例プレゼン、2. 教科書等のまとめ、3. 専門医への質問で進めました。
持田先生は自身が救急外来で経験した急性虫垂炎の症例をもとに、急性虫垂炎の病態、症状、身体所見、診断、治療など全般をまとめました。
途中、放射線診断科 都司先生よりカルテ上でCT画像を映しながら読影に関してコメント頂きました。まず上行結腸を同定し盲腸まで辿り管腔構造が盲端になっているのを探すこと、エコーでもそれは同様であり右下腹部に管腔構造が見えただけではそれが虫垂かどうか判別できないので盲端になっているところまで描出することを説明して頂きました。ただし、腹部エコーの技術を習得できる限界も初期研修中に認識すべきであり、エコーで虫垂を同定・描出することは極めて難しいと思います。非専門医としての私見ですが、腹部エコーでは明らかな胆嚢炎と水腎症がわかれば十分と考えます。画像のモダリティについては、小児ではエコーを優先するが描出が難しければ次は確実に診断するため造影CT、成人では普通の体格なら単純CTでも可とのことでした。
消化器外科 坂本先生からは提示症例への方針決定について、臨床経過、本人の希望や社会背景、コンサルトを受けた時間帯など様々な要素を勘案して相談の上で判断したことを説明頂きました。診療ガイドライン等では治療方針がフローチャートとしてまとめられていますが、実臨床ではそのような図に即して自動的に決めているわけではないということがわかったかと思います。
最後に専門医への質問として虫垂炎疑い例のコンサルトにおける考え方を挙げ、複数の消化器外科医からコメント頂きました。まとめきれませんが方針は状況により多様であり、コンサルト後速やかに手術、一旦抗菌薬投与して日勤帯に手術、膿瘍形成例などに対して抗菌薬を投与し炎症を鎮めた後に手術(interval appendectomy)などが選択肢かと思います。実際の臨床では非専門の内科当直医としては、腹痛の診断が虫垂炎かどうか迷う場面がしばしばあり、そのような時には診断に関するコンサルトをお願いせざるを得ません。虫垂炎例ではありませんが、個人的には同じ症例に対して消化器内科、消化器外科ともお呼び出しして一緒に考えて頂いたこともあり…本当に腹痛診療は難しいと感じています。
他にも研修医・指導医を問わず多くの参加者から自由に質問・コメントがありました。
(追記)
今回は医学生の参加もあり、冒頭で会の主旨を説明しました。その中で「学び方のモデルを示す」意図を簡単に伝えたのですが、年度末も近く改めて整理します(学生・初期研修医向けです)。
初期研修中に達成すべき目標の1つは「型をつくる」ことであると考えています。カンファレンスを通して各聴講者も自身の診療・研修を振り返り、① 診療・プレゼンテーションの型をつくること、② 学び方の型をつくることの2点を、自分ごととして意識して頂きたいと思います。
- 診療・プレゼンテーションの型
OSCEなどで教えられてきたもので、全員共通のフォーマットです。
学会発表を重ねていくと痛感しますが、良い診療を行わなければ良いプレゼンテーションはできません。プレゼンテーションの準備を進める過程で客観的に自分の診療を振り返ることになります。主訴、現病歴、review of systems、既往歴、社会歴等、呼吸数を含む身体所見、検査所見…という一連の”型”には、先達が繰り返してきただけの意味が必ずあり、まずは型通りになぞってできることを目指すべきです。スポーツでいう筋トレ、素振り、パス練習のようなもので、プロ選手でも基本を疎かにすることはないはずです。学生~初期研修中に型を崩すと診療の抜け・漏れが生じ、ミスが起こる可能性が高いです。自然に身体と頭が動くようになるまで、時間がかかっても型を守るよう意識して下さい。今は時間がかかっても型を守り続けた人は、数年後には同じ質を保ったまま数分の1の時間で診療できるようになります。
このカンファレンスではcommon diseaseのシンプルな経過を扱うことが今後も多い見込みですが、そのようなcaseでこそ型に沿った診療に基づいた標準的なプレゼンテーション様式を忠実に守って頂くことを勧めます。
型を守って時間をかけて診療する研修医の方が指導医より診断できる可能性もあります。救急外来から胆嚢炎で消化器内科へ入院依頼した症例に、原発性アルドステロン症の合併を指摘できたのはしつこく診療していた研修医2年目の時でした…が、今では気付くことができないかもしれません。
- 学び方の型
こちらは対象者と状況により多様な型が考えられますが、ひとまずはカンファレンスで提示している”型”に沿って症例ごとに学び方を考えてみて下さい。非専門医にとっての達成目標を考える→独学(主に教科書(内科ならハリソン等)やUpToDate)→残った疑問は専門医に聞く…のサイクルです。
多くの場合、学ぶモチベーションの源泉は症例にあると思います。ただし、何となく診た症例から学べるものは少なく、丁寧に記録し考えた症例でこそ学びが深まります。
学生・初期研修中、また3年目以降の非専門領域における学び方では「どこまで」「どのように」学ぶかを良く考える必要があります。試行錯誤しながら自分にあった型を見付けていけば良いでしょう。このカンファレンスで必ず専門医に来て頂いている理由は、「どこまで」学ぶかのラインを見極めるためです。研修医/非専門医としては、ある程度の独学でわかった気になるところまで辿り着けるのですが、経験不足であったり知識が体系立っておらず部分的であったりと専門医のレベルには及びません。もちろん専門医レベルを目指す必要はないですしできないのですが、まずは学ぶスタートラインを切る段階で自分なりのゴール(達成目標)を漠然とでも良いので定めた方が良いです。「どこまで」学ぶかという目標設定ができれば「どのように」進めていくかは概ね見通しが立つと思います。
具体的には『日常診療で臨床疑問に出会ったとき何をすべきかがわかる本』に全て書いてあります。
(参考1 鈴木の例)
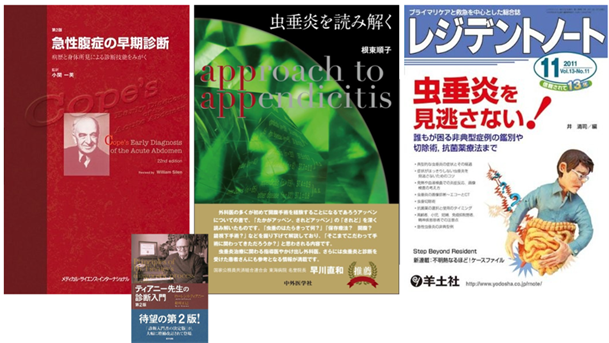
膠原病・腎臓内科の専門医で、シェーグレン症候群の国際コホートに金沢大学に在籍していた頃から参加しています。非専門医としてのアウトプットが必要な場面は主に救急外来ですが、専門診療に比べて時間は短く、そのためのインプットを常にできるかというと難しいです。
当院での本カンファレンスを含めて他院でも医学教育に時間を割いてきたのは、研修医教育に乗じて自分も勉強しようという利己的な理由によります。今回は上記3冊に目を通しました。
『急性腹症の早期診断』は学生時代に旧版を購入し、書き込みしながら読んできました。鑑別診断の神様などと称され、金沢でずっと御世話になってきた大リーガー医のティアニー先生が「医学書オールタイムベスト3」の1冊として紹介されたこともある名著です(残り2冊が気になる方は個人的に聞いて下さい)。1921年初版で、日本語訳の最新版は22版の翻訳です。CTがない時代の優れた外科医がいかに丁寧に病歴・身体所見をみていたか、総論部分は必読です。虫垂炎の章では症状の発生順序について「1. 疼痛(通常は心窩部や臍部で感じられる)、2. 食欲不振、悪心、嘔吐、3. 圧痛(腹部、あるいは骨盤のあらゆる部位で起こりうる)、4. 発熱、5. 白血球増加」と紹介されており、臨床的に有用と感じています。
『虫垂炎を読み解く』は2023年刊の新しい本で、理由は忘れましたが今回のカンファレンスより以前に買って積んでいたものです。「勉強すればするほどわからなくなる」という逆説的な現象があることを本会の冒頭で述べましたが、あらゆる文献をまとめる中で筆者に多くの臨床的疑問が生じていったことが読み取れ非常に面白かったです。わかること(known)が増えると、現在わかっていること(known)とわからないこと(unknown)の境界が見えてくるのです。虫垂の長さを測り続けた研究、虫垂内容液を培養し細菌をまとめた研究が存在することには飽くなき好奇心を感じましたし、虫垂を切除することによって別の疾患に罹患しやすくなるかもしれないという視点は新鮮でした。
虫垂炎のみをテーマにしたレジデントノートが過去にあったことにも気付き、図書室で眺めてみました。寺澤秀一先生による原稿の最後に「初診時に診断できなかったことが医療過誤になるのではなく、1回の受診では非典型的な急性虫垂炎の診断が困難なので、再評価が必要だということを説明しなかったことが、医療過誤になるのである。」という指摘は深く、救急外来での診療はどれだけ注意してもし過ぎることはないと思います。
たまたま偽虫垂炎(pseudoappendicitis)という用語があることにも今回気付きました。Yersinia enterocoliticaという細菌感染は腸間膜リンパ節炎や回腸末端炎を来し発熱・右下腹部痛を呈することから臨床的に虫垂炎と鑑別困難であるとのことです。加えて、Yersinia pseudotuberculosisという名称の細菌もあり、菌血症を来すと肝・脾膿瘍、腹膜炎、化膿性関節炎、腸腰筋膿瘍、骨髄炎、心内膜炎、心筋炎、感染性大動脈瘤、髄膜炎など確かに結核類似の病態を起こす可能性があるようです。以上は同じく図書室にある『Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases 9th edition』からの引用です。紙の教科書は目的のページ近くにある記載をたまたま読むことで知識が広がると思います。
(参考2 日本一賢い医師の例(私見))
カンファレンスの”ついで”に勉強したにしては虫垂炎に時間をかけてしまいましたが、世の中にはとんでもなく高いところにいる医師が存在することをついでに紹介します。
虫垂炎の診察においてはMcBurney, Lanz, Rosenstein, Rovsing, psoas, obturatorといった身体所見があり一部に人の名前がついています。McBurneyって誰…と気になって調べる人がいるという話です。『虫垂炎を読み解く』では「当時の診断の難しさが手術治療の遅れを招いていると考え、この圧痛点を1889年にNew York Surgical Societyで発表し、早期診断に同圧痛点を臨床応用することを説きました。多くの臨床医が同圧痛点を虫垂炎の診断に用いるようになり、数千人の命を救う結果となったと評価されました。」と紹介されており、しみじみ読みました。鈴木は疑い例ではこれら全ての所見を研修医時代からカルテに残していますが、30秒もかからないので診察方法を確認しておくことを勧めます。YouTubeで「フィジカルクラブちゃんねる 虫垂炎」と検索すると、総合診療医の平島修先生がAppe 7 plusとして動画で説明されています。一度会いに行ってハグされたことがありますが、エネルギーに溢れたとんでもない医師の1人です。
『雑誌 総合診療 2020年11月号 診断に役立つ!教育で使える!フィジカル・エポ二ム 身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考』から2つの原稿コピーを添付しました。エポ二ムとは今話題にしてきた、人名にちなんで命名された言葉のことです。まずは飯塚病院 清田雅智先生によるKehr徴候ですが、所見そのものでなく孫引きを繰り返して原本を探し続けた途方もない作業の軌跡(図2)を御覧下さい。清田先生は私が知る限り最も賢い巨人であり、とことんまで突き詰める勉強方法を自然に続けていらっしゃいます。飯塚病院では文献ソムリエと称されており、絶対に真似できませんが世の中には化け物のようにデキる医師がいることを感じて下さい。2つ目は鈴木と同学年で学生時代からの知り合いである膠原病内科 陶山泰博先生によるHeberden結節です。私が金沢大学硬式テニス部、陶山先生が信州大学硬式テニス部で、彼は卒後飯塚病院で清田先生の薫陶を受けた後、聖路加で膠原病の研修を行い今では膠原病教育を牽引する存在になっています。清田イズムを正統に引き継いでおり、もちろんHeberden先生の原著にあたっています。臨床経験の積み上げ方に関する記載は必読です。

文責:リウマチ・膠原病内科/腎臓内科、研修推進部会 研修医養成プロジェクトメンバー、ワーキンググループ 鈴木 康倫